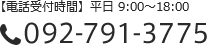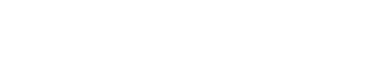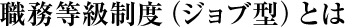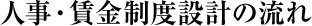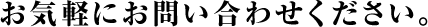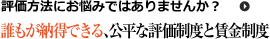「何を評価したらいいかわからない」
「評価基準があいまい」
「賃金体系がただの年功序列になっている」
「女性やシニアが活躍できていない」
人事制度でこのようなお悩みはありませんか?
その原因は、現場の業務に基づいていない評価制度と、あいまいな基準で策定した賃金制度かもしれません。
明確な評価基準は従業員のモチベーションを向上させ、誰もが活躍できる強い組織を作ります。
オープンな賃金制度は、従業員に安心感と満足感をもたらします。
年功序列ではない、役割に応じた職務給の導入で、従業員のモチベーションを向上させましょう。
日本では長年、年功序列型や職務内容を限定しない「メンバーシップ型」が主流でした。しかし近年では、特定の仕事に対して最適な人材を投入する「ジョブ型」が着目され始めました。
ジョブ型が台頭してきた背景には、労働人口の減少や働き方改革、コロナ禍によるテレワーク推進といったワークスタイルの変化や、育児・介護中の方、シニア、外国人など多様な人材を受け入れる必要が出てきたことなどが考えられます。
また、これからの働き方を劇的に変えるDXにおいても職務を明確にしないと導入することはできません。
ジョブ型とは、職務分析を行い、業務内容をジョブディスクリプション(職務記述書)で明示し、職務がどれだけ達成できたかを判定する成果主義タイプの雇用形態です。
そこには共通のモノサシとして「分析され整理された職務基準」がなければ成り立ちません。
| 職務等級制度(ジョブ型) | 職能資格制度 (従来型の制度) |
|
|---|---|---|
| 要件 | 企業から見た戦略的な期待役割を果たすために割り当てられた役割(職務)の価値をベースとした制度 | 社員一人一人の業務遂行能力(保有能力)をベースとする制度 |
| 特徴 | 役割(職務)価値と担当者個々人の業務成果が評価される | 職務遂行能力がベースとなるため、能力を発揮しなくても評価される |
| 評価基準 |
|
|
出典:「職務給の法的論点」西村聡著(日本法令)
人を能力で評価することは難しいものです。
目に見えない能力は他人と比較することができません。
結果、皆が横並びの評価になってしまったり、一部の目立った行動のみが評価されてしまったりと公正に評価することができません。
職務分析を行い、各自の職務とその難易度、職責を明らかにすることによって明確な基準が打ち出せます。
仕事基準のジョブ型の人事評価制度では、その人に割り当てられた職務ができているかできていないかで判断するので評価に迷うことはありません。
職務基準書で従業員側も何をすればよいかが明確になり、納得性の高いシステムが構築できます。
職務分析を行うと各自の職務とその難易度、職責を明らかにでき明確な基準が打ち出せます。
職務を洗い出すと無駄な作業が省け、本来あるべき姿に職務は洗練され、短時間でも効率の良いパフォーマンスを出すことができます。
限定した形での働き方の従業員も活躍する場を得ることができます。
さらに、それぞれがどんなプロセスで何をやればよいか、どのような責任や権限があるのかといった職務の基準が明確になることは、心理的安全性をもたらしパフォーマンスが上がるだけではなく、成長やイノベーションを職場にもたらします。
既存の産業に代わって新しいサービスが生まれてきています。
コロナ禍でリモートワークも普及し、働く場、働き方に対する人々の意識が大きく変わってきています。
育児、介護、治療、副業、ワーケーションなどそれぞれがその状況に応じて、多様な働き方の選択をする未来が見え始めています。
新しい働き方に対応するためには「職務」を分析しないと始まりません。
-
女性社員の活躍と管理職登用
業務プロセス、必要とされる知識が明らかになることにより、総合職や管理職になるために何が必要なのか、何をやればよいのかが明確になり、昇進への不安がなくなります。
性別や残業の有無で評価が変わることがないため、女性社員でも正当な評価が受けられるようになります。
-
多様な働き方に対応
各職務が明確になるため仕事の分担や引き継ぎも容易で、長時間勤務が難しい育児中、介護中、治療中の従業員、障がい者やシニアも難易度を下げることなく働くことができます。
キャリアを諦めることなく、安心して働くことができます。
-
DXに対応
これからの働き方を劇的に変えるDXにおいても職務を明確にしないと導入することはできません。
職務分析で業務の手順を可視化します。
- ・制度の内容が明瞭で、社員が理解しやすい
- ・仕事の役割と、会社への貢献度に応じて正当に評価される
- ・評価の基準が公平で納得性がある
- ・自らの役割と職責が明確で、やるべきことがわかる
- 課題分析
-
- ・現状分析をして経営課題、人事課題を抽出
- ・それぞれの課題をもとに基本方針を確認
- ・人事制度全体の基本設計を行う
- 職務分析
-
- ・職務調査をし、職務を課業ごとに纏める
- ・課業のフローを分析し、難易度や求められる技能、知識などの洗い出しを行う
- ・職務を、本来のあるべき姿に再設計する
- ・職群別の職務基準書の作成
- 賃金設計
-
- ・等級の基準を定める
- ・等級基準に沿って格付けを行う
- ・賃金体系、賃金テーブルの作成
- 評価制度設計
-
- ・評価基準、評価ルールを定める
- ・職群別、階層別での人事考課表の作成
- ・評価者研修により評価方法を統一化する